ハウスメーカーや工務店のチラシや広告でよく目にする注文住宅の坪単価。坪単価の高い安いを比較して費用の目安にする人もいますが坪単価は計算方法で大きく変わります。今回は注文住宅の予算を考える上での重要な
・坪単価の計算方法
・坪単価で注意していくポイント
・坪単価の相場
についてまとめましたので紹介していきます。
坪単価とは?
坪単価とは、注文住宅を建てるときの1坪(タタミ2枚分/およそ3.3平米㎡)当たりの建築費がいくらかかるかを示すものです。家を建てるときにかかる1坪当たりにかかる建築費が坪単価です。本体価格を延べ面積で割った数値として、おおよその目安として一般的にも参考にされています。
坪単価の計算方法
注文住宅の坪単価の計算方法は「建物の本体価格」を「延床面積(坪数)」で割ることより金額を出すことができます。
坪単価=本体価格÷延床面積(坪数)
では実際に計算してみましょう。
・本体価格が2,000万円の延床面積40坪の家を計算した場合の坪単価
本体価格2,000万円÷40坪=坪単価50万円
となります。
延床面積が㎡だった場合の計算方法
延床面積が㎡だった場合は、㎡を坪数に直したほうが計算しやすいです。
・本体価格が2,000万円の延床面積が㎡表記だった場合の坪単価
まず㎡を坪に計算し直します。まず1㎡は、0.3025坪です。
たとえば132㎡の場合、132に0.3025をかけると坪数を算出することができます。
132㎡×0.3025(1坪)=39.9坪
そして、本体価格2,000万円を今計算した坪数39.9で割ることにより坪単価を算出することができます。
本体価格2,000万円÷39.9坪=坪単価50.1万円
この坪単価を一般的に注文住宅を建てるときの費用の目安として参考にされています。
ですがこの坪単価の計算方法や含まれる費用(本体工事費、別途工事費、設計料)の範囲が異なることもあります。費用の範囲が違うと坪単価の金額が変わってきますので、坪単価だけを見てすぐに注文住宅の建築費用が高いか安いかを判断するには注意が必要です。
延床面積と施工面積のどちらで計算しているか?
坪単価の計算で注意しなければならないところがあります。それは坪単価を計算する際に「延床面積」「施工面積」のどちらを使用しているかというところです。
施工面積とは、建築基準法では延床面積に含まれない部分である「バルコニー」「玄関ポーチ」「吹抜け」「地下室」「外部階段」などすべてを合計した面積のことです。施工面積は延床面積には含まれない部分も含まれるため延床面積よりも大きくなります。そのため、延床面積で考えた坪単価より施工面積で考えた坪単価のほうが安くなります。
では実際に、本体価格が3,000万円の家の延床面積と施工床面積のそれぞれの坪単価を計算して比較してみましょう。
・延床面積40坪で計算した場合
本体価格2,200万円÷40坪=坪単価55万円
・施工面積44坪で計算した場合
本体価格2,200万円÷44坪=坪単価50万円
となります。
施工面積で計算した場合のほうが延床面積で計算するよりも坪単価が安くみえます。坪単価を計算するときにどちらを使用するかは明確な決まりがありません。
・A社 坪単価 55万円(延床面積)
・B社 坪単価 50万円(施工床面積)
B社のほうが安く見えるがA社が施工床面積で計算するとA社のほうが安くなる可能性もあります。
坪単価は、延床面積で計算しているのか施工床面積で計算しているかをハウスメーカーや工務店に確認するようにしましょう。
同じ床面積でも形状の違いで坪単価が変わる
床面積が同じ場合でも、本体価格は家の形によって違ってくるため、坪単価も変わります。
たとえば延床面積が同じでも、シンプルな四角の形状の家より出っ張りが多い複雑なデザインの家のほうが費用が増えます。柱や壁、屋根の面積が増えるため材料費もかかり、建物の形状が複雑になるほど工事の時間も長くなるので工事費もかかります。そのため工事費や材料費などの費用が増え、結果として本体価格の費用が高くなり同じ床面積でも坪単価に差が生まれてしまうのです。
坪単価は床面積が小さくなるほど安くなるわけではない
坪単価は延床面積が小さくなるほど坪単価が安くなるということではありません。延床面積が小さくなるほど坪単価が上がっていまいます。なぜなら延床面積が小さくなったとしても、人件費や設備機器や建築資材の運搬費や養成費や仮設費用などの費用は比例して減るわけではないので本体価格は安くならないからです。
では実際に40坪の家とそれより小さい30坪の家の坪単価を計算して比較してみましょう。
・40坪の家
本体価格2,200万円÷40坪=坪単価55万円
・30坪の家
本体価格2,100万円÷30坪=坪単価70万円
このように床面積が小さくなっても本体価格はさほど下がらないため、床面積が小さくなるほど坪単価が高くなります。
1階と2階が同じ床面積でも割合で坪単価が変わる
1階と2階床面積が同じ場合でも面積の割合で坪単価が変わり1階が大きいほど高くなります。
1階と2階が同じ床面積の家と1階が大きく2階が小さい床面積の家を比べると、1階が大きく2階が小さい床面積の家では、屋根や基礎の面積が大きくなるので、その分本体価格が高くなります。そのため同じ床面積でも1階が大きいと屋根や基礎の面積が増え本体価格も高くなり坪単価が高くなるのです。
設備や設備のグレードを上げると坪単価は高くなる
キッチン、バスやトイレなどの設備や仕様のグレードをアップすると本体価格が高くなり坪単価が高くなります。
実際に通常の家と設備や仕様のグレードをあげた家の坪単価を計算し比較してみましょう。
・通常の家
本体価格2,200万円÷40坪=坪単価55万円
・設備や仕様のグレードをあげた家
本体価格2,500万円÷40坪=坪単価62万円
はじめは坪単価55万円だったのに、設備や仕様を追加していくうちに本体価格が高くなり坪単価62万円に・・・。気がつけば坪単価が高くなってしまったということがあるので注意が必要です。いつの間にか予算オーバーということにならないために優先順位を立てて計画しましょう。
坪単価の注意点
家づくりを考えると必ず目に止まるのが、坪単価という言葉です。
坪単価は本当に難しい言葉です。
どうして難しい言葉かといえば、
実は、営業マンの使う「坪単価」とお客さんの使う「坪単価」は意味が違うからです。
どういうことかというと、
営業マンのいう坪単価は、

「建物本体価格」割る坪数のことを指す場合が多いです。
お客さんのいう坪単価は、
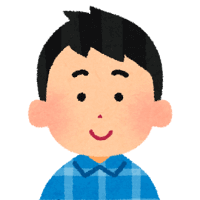
全体でかかった費用を坪数で割ったことを指す場合が多いです。
つまり営業マンのいう坪単価は安い数字を指し、お客さんのいう坪単価は高い数字になります。
注文住宅を建てるには坪単価だけがすべての費用ではない
注文住宅を建てるには坪単価の計算で使用した本体価格だけが費用ではありません。本体価格に含まれていないことが多い別途工事費や諸経費などがかかります。たとえば、地盤改良費や照明器具工事費や水道の引き込みや外構(庭や門など)工事費、カーテン工事費合などは別途工事費であるため本体価格に含まれていなく坪単価の中にも含まれないことが多いです。
そのため注文住宅の予算は、坪単価×延床面積プラス20%〜30%と考えておくと余裕が生まれます。
ハウスメーカーの坪単価相場
大手ハウスメーカー8社の2016年の坪単価です。ハウスメーカーで注文住宅を建てる費用の相場の参考になります。ハウスメーカーの坪単価は地域ごとに坪単価に差があるので注意です。
| ハウスメーカー | 平均 坪単価 (万円) | 平均 建築費用 (万円) | 平均 床面積 (坪) | 平均 床面積 (㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 三井ホーム | 95.9 | 4000 | 41.7 | 137.6 |
| 住友林業 | 95.0 | 3780 | 39.8 | 131.3 |
| ヘーベルハウス | 93.0 | 3254 | 35.0 | 115.5 |
| 積水ハウス | 88.8 | 3729 | 42.0 | 138.6 |
| 大和ハウス | 85.3 | 3430 | 40.2 | 132.7 |
| セキスイハイム | 82.2 | 3060 | 37.2 | 122.9 |
| パナホーム | 81.7 | 3549 | 43.5 | 143.4 |
| ミサワホーム | 74.0 | 2728 | 36.9 | 121.7 |
まとめ
坪単価は、様々な状況により変わります。正確な坪単価で比較したい場合はハウスメーカーや工務店にどのように計算したのかを確認したり資料請求をして比較しましょう。ハウスメーカーによって得意とする構造が違うため坪単価は注文住宅の費用のあくまでも目安としてつかっていきましょう。
